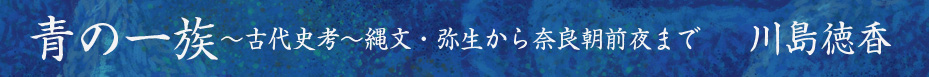
第7章 5世紀後半から6世紀にかけて
5世紀は朝鮮半島との交流が盛んで文物の流入は激しく、人々の意識にも変化があった。歴史では天皇の系譜がそれまで一子相伝の様相を呈していたのが、仁徳の後は三人の息子がそれぞれ帝位を継いだことになっている。また、それまでは第二子か末子が後を継ぐ習慣だったものが、長子から順になった。歴史が実際に書かれた時代に近づき、伝説ではなく事実を書いたということもあるだろう。それまでの天皇はみな百歳の信じられない長寿だったが、反正の在位はたった5年だ。これも史実だからこそかもしれない。『紀』には「群臣が協議して天皇を決めた」というそれまでなかった記述がある。実際に、各豪族がお互いの力量をはかりながら各々が存続できるように天皇の地位に座る人間を選んでいたのだろう。そのことがそのまま表現されている。 『宋書』によれば、443年に倭王の済が宋に朝貢している。このとき済も同行した臣下も同じ将軍号を授与された。つまり、済はリーダーだったかもしれないが連合の盟主に過ぎないのであって、絶対権力を握った大王というわけではなかったことを示す。5世紀の中頃でそうなのだから、仁徳の子供たちが順次帝位を継いだというのも当然疑わしく、彼らはそれぞれ力を持った豪族の首長だったと考えるのが妥当だ。 そして、豪族たちの権力を巡る抗争の中から本当の中央集権に至る道が現れてくる。
1 5世紀後半の古墳
1-1 市野山古墳/1-2 土師ニサンザイ古墳・軽里大塚古墳/1-3 両宮山古墳
5世紀後半になると大型古墳の数はずっと減る。また、近畿外で古墳の増える地域ができるなど情勢が変わる。
5世紀後半にできる大型古墳は以下の通り。
◎200メートルを越す古墳
佐紀 ヒシアゲ古墳(218㍍ 磐之媛陵に治定)
百舌鳥 土師ニサンザイ古墳(290㍍ 反正天皇陵墓参考地 堺市)
古市 市野山古墳(227㍍ 允恭天皇陵に治定 藤井寺市)
古市 岡ミサンザイ古墳(245㍍ 藤井寺市) 5世紀末
吉備 両宮山古墳(206㍍ 岡山県赤磐市)
◎100メートル越えの古墳
百舌鳥 田出井(たでい)山(やま)古墳(148㍍反正天皇陵に治定 堺市)
古市 軽里大塚古墳(190㍍ 羽曳野市)
和泉 淡輪ニサンザイ古墳(173㍍ 泉南市)
馬見 掖上鑵(わきがみかん)子(す)塚(づか)古墳(150㍍ 御所市)
狐(きつ)井(い)城山(しろやま)古墳(140㍍ 香(か)芝(しば)市) 5世紀末
そのほかに、茨城県に4基、群馬県に3基、岡山県に2基
福岡・大分・宮崎・愛知・栃木・埼玉・千葉県に各1基
ヒシアゲは佐紀古墳群での、掖上鑵子塚は馬見古墳群南部での最後の大きな古墳になる。掖上鑵子塚は葛城氏の円大臣(つぶらのおおおみ)や眉輪王(まよわのみこ)の墓という説があるが、形が帆立貝形に近く被葬者は海洋族の可能性もあると思う。狐井城山は周囲で竜山石の石棺片が採集されていて、巣山系の後裔首長かと思える。淡輪ニサンザイは別名宇度墓といい、五十瓊敷入彦(いにしきいりひこ)の墓と言われるが、紀小弓の墓という伝承もある。紀氏と宇土半島と和泉は関わりが深いことがわかる。
1―1 市野山古墳
市野山古墳は古市の中でもいちばん北の位置に作られた。中津山に接している。陪塚は唐櫃山(からとやま)古墳(53㍍)・長持山古墳(40㍍円墳)・宮の南塚古墳(40㍍円墳)・衣縫塚(いぬいづか)古墳(2㍍円墳)。唐櫃山からは阿蘇溶結凝灰岩の家形石棺が、長持山からも刳抜式家形石棺が出ている。同じく古市古墳群の5世紀前半に作られた墓山古墳と同形同規模だという。
6章1―4項で触れたが、墓山古墳に接する青山地区は若狭や丹後に関係があると私は見ている。墓山も陪塚は方墳ばかりで、長持形石棺は加古川産の竜山石製で播磨勢の関与が認められ、大量の滑石製品が出ていて丹後の玉造りの伝統をうかがわせる。
三島にある5世紀中頃築造の太田茶臼山古墳(茨木市)と市野山は同形だという。そして5世紀初頭に但馬に作られた池田古墳(朝来市)と共通点があるという。太田茶臼山は誉田御廟山古墳と相似だ。池田古墳は大日下王や物部氏と関わりが深いが、23体もの水鳥埴輪が出るなど山陰文化の色も残している古墳だ。
こうしてみると、朝鮮半島侵攻の主勢力の九州勢が眷族になっているものの、市野山古墳の被葬者は丹後・丹波・播磨を取り込んだ吉備主体の応神天皇の後裔に見える。古墳のある場所もそれを示している。
1―2 土師ニサンザイ古墳・軽里大塚(かるさとおおつか)古墳
土師ニサンザイは5世紀後半に作られた。この古墳のあるところはその名の通り土師町だから陶工がいたところだろう。そして隣の陵南町は5世紀から操業を始める鉄生産所のひとつだから、物部氏の地として間違いないと思う。そしてこれが軽里大塚古墳と相似形だという。
百舌鳥の田出井山古墳が現在反正天皇陵に治定されているが、天皇陵としては小さすぎるので、土師ニサンザイ古墳を反正天皇陵にあてる説がある。反正天皇についてはこの後の2項で、土師ニサンザイ古墳・軽里大塚古墳の被葬者については6項で述べる。
1―3 両宮山(りょうぐうさん)古墳
畿内以外での200メートル越えの古墳は岡山県赤磐市にある両宮山古墳(206㍍)だけだ。これは大仙陵の5分の2の相似形で濠が畿内型だという。仁徳と岡山の関わりについては『記』に、吉備の海部直の娘、黒媛を追って仁徳が吉備の山方面に行き、そこで食事をする話がある。これが両宮山古墳の地域と仁徳の関わりを示すものではないか。赤磐市は備前にあるが、造山・作山の両巨大古墳がある備中は窪屋氏の本拠だ。仁徳は吉備の巨大な力を恐れ、備前の豪族と組むことで備中の勢力を削ぐことを考えたと思われる。
両宮山古墳はその規模に似合わず、葺石も埴輪もない。陪塚とされる和田茶臼山(55㍍帆立貝形)にもない。陶工などを手配する暇がなかったのか、いかにも急ごしらえといった様相だ。両宮山の後には帆立貝形の森山古墳(82㍍)、朱千(しゅせん)駄(だ)古墳(85㍍)、小山(こやま)古墳(67㍍)、廻lり山(まわやりま)古墳(47㍍6世紀前半)と規模を縮小しながらも古墳の造営が続く。森山古墳には葺石・埴輪があり、朱千駄古墳から後は埴輪がある。