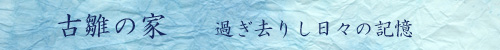
●本を読む能力● 2004年3月15日
読書は訓練が必要な、一種の技術である。そして、その技術を習得した者には、既にしてそのありがたみや自分の特異性がわからない。読書に限らず、どんな技術にも言えることだけれど。
神林同盟会員の例を二つ挙げてみよう。
一人はコンピュータ関係の仕事をしている人。本を読むのが速い。曰く。「部下に、マニュアルを読んでこいって言ってるのに、一週間経っても一冊読み切らないんだよね、あんなものは一晩で読めるだろうが……」。ソフトのマニュアルは、普通の人には、まず読めない。ソフトをいじるのが好きな人だって、マニュアルを読むのは苦痛だろう。だいたい、分厚いあの手のものが一晩で読めるものか。
もう一人はデザインの仕事の傍らマンガを描いている。子供の時にマンガを買ってもらえなかったので、日本文学全集(子供向けのものではない)などに読みふけったという変わり者である。で、「千冊の本を読むのがすごいって言われるけど、一日、一冊読んだら、三年で千冊を越えるでしょ(にっこり)」。そんな人ばかりだったら出版業界にこんな不況風は吹いていない。
こういう人たちは、「たくさんの本が読める」という技術を身に付けているのだ。しかし、そんなことを特殊なことだとは感じない。
『鋼の錬金術師』に、本を一度読むと、それをすべてそのまま覚えていて、再現できるという、忍法帖みたいな特殊能力を持った女の子シェスカが出てくるが、彼女はイディオット・サヴァンかと思われるほどに思考能力が欠落しているため、その能力を活かせず、「本を読む以外は何をやっても鈍くさくて、どこに行っても仕事ももらえなくて、そうよダメ人間だわ、社会のクズなのよう(泣)」「私なんか本にのめりこむことしかできないダメ人間」と自分を卑下している。これっていったい何の戯画なのか、と思わず考えてしまう。被害妄想的に考えると、「そいつはオレのことを言っているのか!?」みたいなことになるわけだが、まあ実際、読んで覚えているのに、この子のようにそれが思考のプラスになるわけでないなら、「何の役にも立たない」のは理の当然である。それはともかく、仕事のためでもなく本を読む人は、「本を読むなんていう何の役にも立たないこと」は、実は習得された技術であって、誰にでも出来ることではないということを忘れがちではないかと思う。
本を読む技術は、まずは文字が読めるところから始まる。アルファベット、いろはに習熟し、文盲ではなくなって初めてまとまった単語が読めるようになる。その後、文章が何とか読めるようになるという段階を経て、何枚かのまとまった作品が読め、ついには長い一冊の本も読めるようになるのである。そして一旦読めるようになると、既に獲得した人間にとっては、どうやって読めるようになったのか思い出すのも困難なほど、自然なものになる。
友人の子供に、大層利発な小学校一年生がいる。幼稚園の頃から普通に本を読んでいるので、入学当初に国語の教科書を見て、「私をバカにしているのか」と怒ったそうだ。自分が二、三年前に通り抜けてしまい、もうどのように覚えたかも忘れてしまったようなものを改めてやらされるのでは、そう思っても仕方がないだろう。そのような彼女には、大学生になっても一冊の新書が読み通せないというような現実があることは、想像が及ばないことにちがいない。
しかし、ハリ・ポタやナルニアを読破してしまったこのたいそう利発な少女にも、読んでも理解できないことは多々あるだろう。経済学や哲学の本は読めない。そういう本を読むためには、特殊な語彙(知識)や思考が要求されるから。ソフトのマニュアルだって読めない。そのソフトを扱っていない人には、読めても本当には理解できないから。また、大人の恋を扱った小説も、ドストエフスキーやカフカも無理に違いない。当たり前すぎる話だが、果たしてはっきりと当たり前だと認識されているだろうか?
というのも、文学を読むことにも特殊な技術が必要だということは、まるで忘れられているかのようだからだ。あるいは文学を読むということは、ある約束事が律する共同体の中に入っていくことだということが、それはあまりにも意識されていないように思えるからだ。
そんなようなことを漠然と思いながら、「文学を読む」ということについて考えてみた。興味のある方はどうぞそちらも覗いて見て下さい。