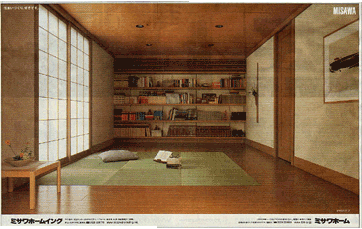第10回 「本」
ミサワホーム/2001年6月14日(木)日本経済新聞朝刊31面
昔、「お宅訪問」といった企画の取材記事を書いていたことがある。記事といっても、それは広告のようなもので、スポンサーの不動産会社が斡旋した物件に住んだ人の家に訪ねていき「この家に決めて良かった」、みたいな言葉を引きだして書くのである。毎月一日、週末を潰されるのは痛かったが、僕にはこの仕事が楽しかった。一億円近くする家を建てた人も、狭い中古のマンションをローンで購入した人も、そこでは同じように紹介することができた。出てくれる家庭が少なくて、都合のいい家ばかりを選ぶ余裕がなかったのだ。それに、小さな家でも、それを買った家族の顔は生き生きとしていたし、一億の家に住んでも幸せは大して変わらないのだな、というのが印象であった。そんなことよりも僕の興味はいつもその家庭の本棚にあった。家の美しさや住人の職業や見かけよりも、寝室や子ども部屋の本棚を必ず僕は最初にチェックするようになっていた。都合の悪い部屋を見せない家庭もあったが、本棚を隠す家はなかった。しかし、今回の広告に出てくるような本棚は見たことがない。
今回はミサワホームの企業広告である。全7段という、1面の半分近くにあたるスペースに、目を引く大きな活字はひとつもない。その代わり広告面全体に1枚の写真が配置されている。そこに写されているのは、15畳ほどのがらんとしたフローリングの部屋。その中央部は琉球畳のスペースになっていて、障子越しの陽光が射し込んでいる。そして厚めの座布団と積み上げられた5冊の本、その上に置かれた黒縁眼鏡、ちょっと席を外した主人を待つように広げられた本がブックイーゼルに固定されている。部屋の右手には絵と花が架けられ、左手前にも花が活けられ、天井に無粋な照明器具などはぶら下がっていない。そして奥は一面の書棚。とはいっても、そこはぎっしりと本で埋め尽くされているわけではなく、模型や子どもの写真などが、ところどころにある隙間を埋めている。
よく観察して欲しい。これはコピーライターでもデザイナーでもなく、カメラマンですらもなく、もっぱらインテリアデザイナーの広告として成立しているからだ。とにかく日経読者が「いいな」と、いやされるような一室を作り上げること。それだけが目的であろう。だから2001年6月14日の日本人の集合意識が「いいな」という一室への指向が、ここにはあるはずである。
ところで集合意識は実体のないイメージに過ぎないから、飾られた絵や花や本は、まるで夢の中のようにぼんやりしたイメージに収まっている。おそらく百科事典や全集で占められた本達は、その頁をめくれば何も書かれていないのではないかとすら思える。書棚に置かれた雑貨も同様で、赤い帽子をかぶった子どもの写真さえも、程良くピントがぼけていて、何か抽象的なぬくもりをわずかに発散するばかりだ。この夢の部屋には、DVDもパソコンもケイタイ存在しない。 休日の昼下がりを愉しむのにふさわしい小道具として、当然のように本が選ばれているからだ。 これは、21世紀に書物が復権しようとしている兆しなどでは決してない。むしろその逆で、書物はもっぱら回顧されるべき懐かしい過去として、その背中を向けているのだ。この部屋には20世紀に発明されたものはひとつといってなく、昼下がりの読書という紋切り型だけがそこでいつまでも、見果てぬ白昼夢としてわたしたちの想像力の貧しさを笑っているようで、悲しい。